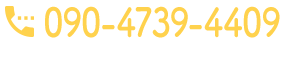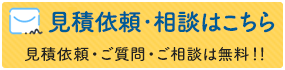屋根コロニアルの塗装状況。
2007年9月20日
どうも、先日の連休に鬼怒川温泉に行ってきましたが、渓谷対岸の緑化工事で、道路がガードレールごと崩落する現場を目の当たりにした筒井塗装です。
建設業は安全第一で!という意味をしみじみ噛み締め、とても気分的にゆっくりする気分になれなかった良い思い出です。
さて、珍しくほったらかしにしておりましたが、ちょっとコロニアル屋根の塗装について調べものをしておりました。
まずはこちらのコロニアル屋根をご覧ください。
 屋根塗装、塗装前。
このコロニアルと屋根材、砂と言うか土というか、無機質の材質でできてます。
ちょっと前に作られたものでは、恒久性を強めるため、
今は使用が禁止になっている石綿が入っていました。
(今新規で作られているものには入っておりません)
スレートやコロニアルは塗装しないからといってすぐ壊れるものではないのですが、
砂状になっていくものなので、劣化するともろくなります。
ではどうすればよいかというと、その劣化を止めるために塗装すればよい訳なんですけど。
塗装というものは、本来表面に塗膜として形成していないといけないわけですね。
その塗膜の膜厚の構成成分が紫外線や雨風を凌いでくれる訳です。
塗装は劣化を止める。それ以上劣化をさせない。という意味での塗装だとしたら、
劣化してしまったものを守る能力が高い塗料は別の組織じゃないのかい?
気づいてしまいました。いや、気づかなきゃいけなかった!(気づきたくなかった気もしますけど)
いくら良い塗料を塗っても、くいつきが悪い劣化した物の上に塗っていたのでは、意味がない!
そうなんです。
劣化度合いをある程度判断した上で塗装をしなくてはいけないんです。
塗料性能スペックそのものが良くなってきている昨今では、とりあえず下塗に、
専用のシーラーをしとけば大丈夫みたいな風潮がありますが、
そうではなく、「基材にあわせた正しい下塗材があるだろう」もとで
「塗料を使用する」べきだと思います。
色をつけてしまうと仕上がりは一緒というか、あまり違いが判らないということは良くあります。
私たちは塗料を使ってきれいに見せることが仕事ですから。
でも、ちゃんと品物について正しい認識や、やってみて塗料や施工の良し悪しを判断できるぺんきやが、
胸張って歩ける業界にしたいですよね。
で、話は戻りまして、劣化したものに吸い込ませて強度を出す塗料というと、
一般屋根用塗料の中ではエポキシ系の下塗材がよいのでは?ということで、
下塗り 2液型 強溶剤エポキシ塗料 (大日本塗料 マイティーエポシーラー)
上塗り 水系 アクリル変性シリコン塗料 (大日本塗料 水性リフレッシュシリコン)
という仕様でやってみました。
つい、このあいだまで「2液型の溶剤の上に、水性塗料は良くない」という話がありましたが、
しっかり乾燥させる時間があるなら全く問題ありません。
塗料というのは指触乾燥といって、指で触れられる状態なら、2回目の塗装を実行できるというルールがあります。
当然、材料や塗料や条件によってすべての塗料がそういうわけではありません。
その際、溶剤成分が違うものは重ね塗りできないんですね。
しかしそれは「完全乾燥していない」条件下での話。完全に乾燥してしまえば全く問題ありません。
むしろ、吸い込んだ塗料が乾燥すれば、吸い込みムラや剥がれなど起きる心配がありません。
その条件をこなして仕上げた塗装がこちら
屋根塗装、塗装前。
このコロニアルと屋根材、砂と言うか土というか、無機質の材質でできてます。
ちょっと前に作られたものでは、恒久性を強めるため、
今は使用が禁止になっている石綿が入っていました。
(今新規で作られているものには入っておりません)
スレートやコロニアルは塗装しないからといってすぐ壊れるものではないのですが、
砂状になっていくものなので、劣化するともろくなります。
ではどうすればよいかというと、その劣化を止めるために塗装すればよい訳なんですけど。
塗装というものは、本来表面に塗膜として形成していないといけないわけですね。
その塗膜の膜厚の構成成分が紫外線や雨風を凌いでくれる訳です。
塗装は劣化を止める。それ以上劣化をさせない。という意味での塗装だとしたら、
劣化してしまったものを守る能力が高い塗料は別の組織じゃないのかい?
気づいてしまいました。いや、気づかなきゃいけなかった!(気づきたくなかった気もしますけど)
いくら良い塗料を塗っても、くいつきが悪い劣化した物の上に塗っていたのでは、意味がない!
そうなんです。
劣化度合いをある程度判断した上で塗装をしなくてはいけないんです。
塗料性能スペックそのものが良くなってきている昨今では、とりあえず下塗に、
専用のシーラーをしとけば大丈夫みたいな風潮がありますが、
そうではなく、「基材にあわせた正しい下塗材があるだろう」もとで
「塗料を使用する」べきだと思います。
色をつけてしまうと仕上がりは一緒というか、あまり違いが判らないということは良くあります。
私たちは塗料を使ってきれいに見せることが仕事ですから。
でも、ちゃんと品物について正しい認識や、やってみて塗料や施工の良し悪しを判断できるぺんきやが、
胸張って歩ける業界にしたいですよね。
で、話は戻りまして、劣化したものに吸い込ませて強度を出す塗料というと、
一般屋根用塗料の中ではエポキシ系の下塗材がよいのでは?ということで、
下塗り 2液型 強溶剤エポキシ塗料 (大日本塗料 マイティーエポシーラー)
上塗り 水系 アクリル変性シリコン塗料 (大日本塗料 水性リフレッシュシリコン)
という仕様でやってみました。
つい、このあいだまで「2液型の溶剤の上に、水性塗料は良くない」という話がありましたが、
しっかり乾燥させる時間があるなら全く問題ありません。
塗料というのは指触乾燥といって、指で触れられる状態なら、2回目の塗装を実行できるというルールがあります。
当然、材料や塗料や条件によってすべての塗料がそういうわけではありません。
その際、溶剤成分が違うものは重ね塗りできないんですね。
しかしそれは「完全乾燥していない」条件下での話。完全に乾燥してしまえば全く問題ありません。
むしろ、吸い込んだ塗料が乾燥すれば、吸い込みムラや剥がれなど起きる心配がありません。
その条件をこなして仕上げた塗装がこちら
 屋根塗装、塗装後。
このように、下塗を入れしっかり乾燥させると、一回しか塗らなくても、水性塗料にもかかわらず、吸い込みムラがおきず、きれいなつやを出してくれます。
密着力も強いので、屋根の塗装はこういうしっかりした塗料選択が必要です。
当然このほかにも、工程として縁切りを行ったり、屋根の塗り方に気を使ったりと、こだわりポイントはペンキ屋さんによって色々あると思いますので、楽しく話しをしてくれる塗装店さんと仲良くなっていただきたいと思います。
屋根塗装、塗装後。
このように、下塗を入れしっかり乾燥させると、一回しか塗らなくても、水性塗料にもかかわらず、吸い込みムラがおきず、きれいなつやを出してくれます。
密着力も強いので、屋根の塗装はこういうしっかりした塗料選択が必要です。
当然このほかにも、工程として縁切りを行ったり、屋根の塗り方に気を使ったりと、こだわりポイントはペンキ屋さんによって色々あると思いますので、楽しく話しをしてくれる塗装店さんと仲良くなっていただきたいと思います。
 屋根塗装、塗装前。
このコロニアルと屋根材、砂と言うか土というか、無機質の材質でできてます。
ちょっと前に作られたものでは、恒久性を強めるため、
今は使用が禁止になっている石綿が入っていました。
(今新規で作られているものには入っておりません)
スレートやコロニアルは塗装しないからといってすぐ壊れるものではないのですが、
砂状になっていくものなので、劣化するともろくなります。
ではどうすればよいかというと、その劣化を止めるために塗装すればよい訳なんですけど。
塗装というものは、本来表面に塗膜として形成していないといけないわけですね。
その塗膜の膜厚の構成成分が紫外線や雨風を凌いでくれる訳です。
塗装は劣化を止める。それ以上劣化をさせない。という意味での塗装だとしたら、
劣化してしまったものを守る能力が高い塗料は別の組織じゃないのかい?
気づいてしまいました。いや、気づかなきゃいけなかった!(気づきたくなかった気もしますけど)
いくら良い塗料を塗っても、くいつきが悪い劣化した物の上に塗っていたのでは、意味がない!
そうなんです。
劣化度合いをある程度判断した上で塗装をしなくてはいけないんです。
塗料性能スペックそのものが良くなってきている昨今では、とりあえず下塗に、
専用のシーラーをしとけば大丈夫みたいな風潮がありますが、
そうではなく、「基材にあわせた正しい下塗材があるだろう」もとで
「塗料を使用する」べきだと思います。
色をつけてしまうと仕上がりは一緒というか、あまり違いが判らないということは良くあります。
私たちは塗料を使ってきれいに見せることが仕事ですから。
でも、ちゃんと品物について正しい認識や、やってみて塗料や施工の良し悪しを判断できるぺんきやが、
胸張って歩ける業界にしたいですよね。
で、話は戻りまして、劣化したものに吸い込ませて強度を出す塗料というと、
一般屋根用塗料の中ではエポキシ系の下塗材がよいのでは?ということで、
下塗り 2液型 強溶剤エポキシ塗料 (大日本塗料 マイティーエポシーラー)
上塗り 水系 アクリル変性シリコン塗料 (大日本塗料 水性リフレッシュシリコン)
という仕様でやってみました。
つい、このあいだまで「2液型の溶剤の上に、水性塗料は良くない」という話がありましたが、
しっかり乾燥させる時間があるなら全く問題ありません。
塗料というのは指触乾燥といって、指で触れられる状態なら、2回目の塗装を実行できるというルールがあります。
当然、材料や塗料や条件によってすべての塗料がそういうわけではありません。
その際、溶剤成分が違うものは重ね塗りできないんですね。
しかしそれは「完全乾燥していない」条件下での話。完全に乾燥してしまえば全く問題ありません。
むしろ、吸い込んだ塗料が乾燥すれば、吸い込みムラや剥がれなど起きる心配がありません。
その条件をこなして仕上げた塗装がこちら
屋根塗装、塗装前。
このコロニアルと屋根材、砂と言うか土というか、無機質の材質でできてます。
ちょっと前に作られたものでは、恒久性を強めるため、
今は使用が禁止になっている石綿が入っていました。
(今新規で作られているものには入っておりません)
スレートやコロニアルは塗装しないからといってすぐ壊れるものではないのですが、
砂状になっていくものなので、劣化するともろくなります。
ではどうすればよいかというと、その劣化を止めるために塗装すればよい訳なんですけど。
塗装というものは、本来表面に塗膜として形成していないといけないわけですね。
その塗膜の膜厚の構成成分が紫外線や雨風を凌いでくれる訳です。
塗装は劣化を止める。それ以上劣化をさせない。という意味での塗装だとしたら、
劣化してしまったものを守る能力が高い塗料は別の組織じゃないのかい?
気づいてしまいました。いや、気づかなきゃいけなかった!(気づきたくなかった気もしますけど)
いくら良い塗料を塗っても、くいつきが悪い劣化した物の上に塗っていたのでは、意味がない!
そうなんです。
劣化度合いをある程度判断した上で塗装をしなくてはいけないんです。
塗料性能スペックそのものが良くなってきている昨今では、とりあえず下塗に、
専用のシーラーをしとけば大丈夫みたいな風潮がありますが、
そうではなく、「基材にあわせた正しい下塗材があるだろう」もとで
「塗料を使用する」べきだと思います。
色をつけてしまうと仕上がりは一緒というか、あまり違いが判らないということは良くあります。
私たちは塗料を使ってきれいに見せることが仕事ですから。
でも、ちゃんと品物について正しい認識や、やってみて塗料や施工の良し悪しを判断できるぺんきやが、
胸張って歩ける業界にしたいですよね。
で、話は戻りまして、劣化したものに吸い込ませて強度を出す塗料というと、
一般屋根用塗料の中ではエポキシ系の下塗材がよいのでは?ということで、
下塗り 2液型 強溶剤エポキシ塗料 (大日本塗料 マイティーエポシーラー)
上塗り 水系 アクリル変性シリコン塗料 (大日本塗料 水性リフレッシュシリコン)
という仕様でやってみました。
つい、このあいだまで「2液型の溶剤の上に、水性塗料は良くない」という話がありましたが、
しっかり乾燥させる時間があるなら全く問題ありません。
塗料というのは指触乾燥といって、指で触れられる状態なら、2回目の塗装を実行できるというルールがあります。
当然、材料や塗料や条件によってすべての塗料がそういうわけではありません。
その際、溶剤成分が違うものは重ね塗りできないんですね。
しかしそれは「完全乾燥していない」条件下での話。完全に乾燥してしまえば全く問題ありません。
むしろ、吸い込んだ塗料が乾燥すれば、吸い込みムラや剥がれなど起きる心配がありません。
その条件をこなして仕上げた塗装がこちら
 屋根塗装、塗装後。
このように、下塗を入れしっかり乾燥させると、一回しか塗らなくても、水性塗料にもかかわらず、吸い込みムラがおきず、きれいなつやを出してくれます。
密着力も強いので、屋根の塗装はこういうしっかりした塗料選択が必要です。
当然このほかにも、工程として縁切りを行ったり、屋根の塗り方に気を使ったりと、こだわりポイントはペンキ屋さんによって色々あると思いますので、楽しく話しをしてくれる塗装店さんと仲良くなっていただきたいと思います。
屋根塗装、塗装後。
このように、下塗を入れしっかり乾燥させると、一回しか塗らなくても、水性塗料にもかかわらず、吸い込みムラがおきず、きれいなつやを出してくれます。
密着力も強いので、屋根の塗装はこういうしっかりした塗料選択が必要です。
当然このほかにも、工程として縁切りを行ったり、屋根の塗り方に気を使ったりと、こだわりポイントはペンキ屋さんによって色々あると思いますので、楽しく話しをしてくれる塗装店さんと仲良くなっていただきたいと思います。