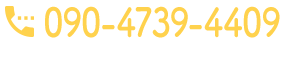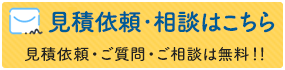錆の構成と錆止塗装についての科学的解説。
2007年3月3日
化学や科学物理、力学なんかが大好きなのに、数学でくじけた筒井です。
今回は錆がどうしてできるかを考えてみます。
錆というものは、大きく捉えると、酸化鉄のことです。
普通に錆びるという現象は、鉄と空気中の酸素や水分、要するに「O2」の影響で、2つの反応が同時に起きているのです。
2つの反応とは、陽極反応(アソート反応)と陰極反応(カソート反応)、電極反応・イオン分解ですね。
・・・えー、皆さんついてきてます?(笑)
電極e-というものは構成原子によって数はまちまちですが、プラスとマイナス同じ数ずつ持っているわけです。
陽極反応とは鉄のイオン分解です。 Fe=Fe2+2e- って式です。
陰極反応とは酸素と水分ですね。 O2+2H2O+4e-=4OH-・・・だったような気がします。
ここで陽極反応でできたものと陰極反応でできたものそれぞれが、くっついちゃうわけです。
生成されたものは、安定した存在になろうとしているからです。
で、このくっついたものがさらに酸化させられて赤錆が発生します。
式で言うと、
2Fe++2OH-+O2→Fe(OH)2-→Fe(OH)3→2FeO・OH又はFe2O3・3H2O
もはや式だとわからないと思います。私もなんだか、さっぱりですw
要するに矢印の進む方向に錆が進行する訳ですが、この式を逆に考えると、「酸素」「水」を遮断してやれば、錆は発生しにくい、ということが導き出せます。
鉄部を空気や水分から遮断する方法・・・それが「塗装」なわけです。
塗料によって、空気透過率や酸素透過率は違うので、錆止め効果がまちまちである、という結果はありますが、塗装工事によって錆を止めることができる、ということも事実です。
錆でお困りの方、ぜひ当店筒井塗装にご相談くださいませ!